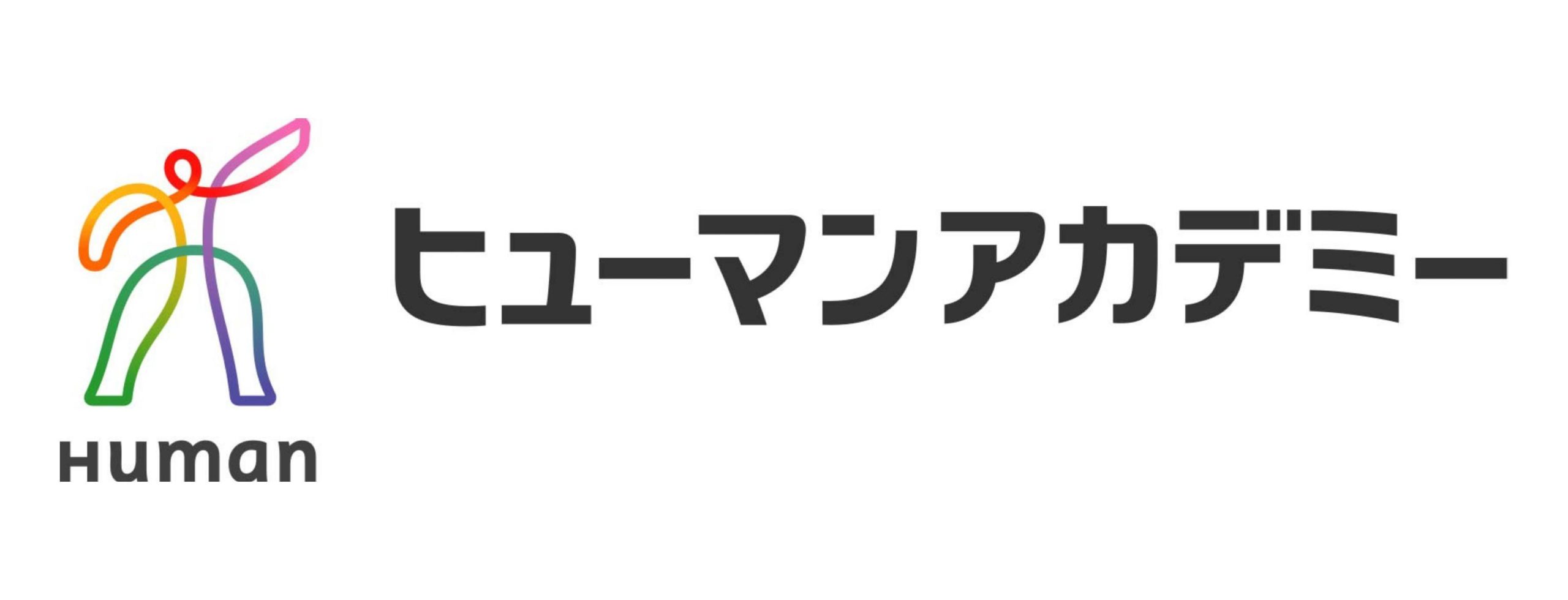当サイトはこれから日本語教師を目指す方のために、日本語教師になる方法、仕事のやりがいや魅力はもちろん、日本・世界で活躍されている約250名の日本語教師のアンケートに書かれた給料に関する情報なども掲載しています。
私自身元日本語教師です。周りに憧れていた海外で働く夢を叶えた人も多いですが、仕事の魅力だけでなく給与などの待遇面も知っていただきたいためです。
やっぱり日本語教師を目指したいみなさんへ
420時間養成講座の修了生による口コミや選び方・注意点も掲載しています。修了生が多いのは1位は圧倒的にヒューマンアカデミー、2位 KEC、3位 アルファ国際学院
国内で教える89名の日本語教師の方に回答いただいたアンケートでは養成講座修了生のうち、約4割弱がヒューマンアカデミー生でした。その他はKEC、千駄ヶ谷日本語教育研究所が1割。実践を特に重視したい方にはKECもおすすめです。
大手の安心感・利便性を求めている方はヒューマンアカデミーをおすすめします。
- 最大手で全国に23校舎
- 受講生・卒業生が圧倒的に多い
- 振替制度など大手ならではのサポートが充実
- 土日も開講していて学びやすい
- 日本語教育能力検定試験の合格率が約70%と高い *2021年度実績
資格大手では珍しく古くから日本語学校も運営し、日本語教育能力検定試験の赤本は受験生の中で必需品とも言われるほど。参加者には受講料の割引もある無料説明会等チェックしてみてください。
コロナ対策として無料説明会と理論科目の授業がオンラインになったようです。
日本語教師になるには
日本語教師になる方法①
養成講座420時間
- ほとんどの求人で求められる養成講座420時間コースとは?
- 養成講座420時間スクールを選ぶポイント
- 地域別 日本語教師養成講座420時間 127校 比較一覧
- 養成講座420時間って何を勉強するの?
- 日本語教師養成講座420時間 よくある質問とその答え
- 日本語教師養成講座420時間 費用は平均「57万円」と注意事項
養成講座420時間 新着口コミ
実際に養成講座に通った方の口コミを新着順に掲載しています。
最大手
ヒューマンアカデミー
420時間コース
働きながら420時間へ通いたい方に特におすすめ
- 校舎数No.1! 全国23校舎。あなたの町にもきっとある♪
- 無料説明会もオンライン対応!
- 受講申込みも来校なしでOK
- 受講もオンライン対応。理論部分はオンラインで自分のペースで学べます。
- 自分のペースで理論を学んだ後、実践科目は通学で生講義。さらに安心。
日本語教師になる方法②
日本語教育能力検定試験合格 *合格率25%
日本語教師になる方法③
大学・大学院に通う
みんなの日本語教師 海外 経験談
新着 経験談
地域・エリア別
みんなの日本語教師 日本国内 経験談
当サイト人気スクール 420時間養成講座
- 1位
-
ヒューマンアカデミー
最大手で人気No1!
無料説明会もオンライン対応 講座の40%が実技授業- 北海道から沖縄まで全国23校舎
- 授業は理論科目がオンライン
- 自分のペースでじっくり理論を勉強した後、通学で実践科目が学べる
- 開講3ヶ月前には満席になるクラスも
- ママと学生は最大28,620円割引
→ ヒューマンアカデミーの資料請求はこちら
- 2位
-
KEC日本語学院
1人50回以上の演習が出来る
- 理論より演習に重きを置いた講義
- 教案作成など演習の準備は大変だが指導技術を数多く学べる
- 6教室 新宿1校/他関西5校
- 3位
-
アルファ国際学院
充実の教育実習80時間
- 経験豊富な一流の専門家講師陣
- フレキシブルな受講スタイルで単位取得可
- 5教室 東京/大阪 他